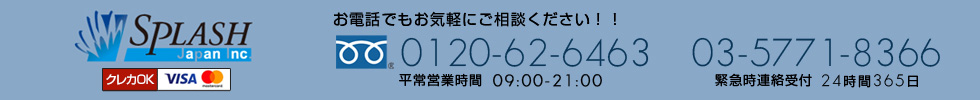スマートフォンが普及するのに伴って、SNSを利用する人も増えていますよね。最近ではご年配の方の利用者や企業が宣伝のために利用するケースも増えてきています。
利用者が増えていく中、利便性も高まっていきますが、それと同時にSNSでのトラブルも増加傾向にあります。
SNSユーザーからの誹謗中傷で、タレントが自殺してしまったという痛ましい事件は記憶に新しいでしょう。このほかにも多くのトラブルがSNSでは起きています。
今回は、SNSの中でも特にトラブルが多く報告されているTwitterにフォーカスをあてて、トラブルの事例やTwitterでのトラブルに巻き込まれないための基本的な対策、そして万が一トラブルに巻き込まれてしまったときに取るべき行動について詳しく解説していきます。
Contents
よくあるTwitterでのトラブル事例
Twitterを利用する際に様々なトラブルの可能性がありますが、具体的な事例をご紹介していきます。
誹謗中傷を受ける
Twitterでの誹謗中傷を受けて自殺や自殺未遂をする人は、芸能人だけでなく一般の方にも多くいらっしゃいます。
不特定多数のユーザーの前で誹謗中傷を書き込まれることで、実際には数人のユーザーしか書き込んでいないのに、周りにいる全員が敵に感じてしまい大きな精神的ダメージを受けてしまいます。
Twitterアカウントを乗っ取られる
Twitterのアカウントが乗っ取られてしまうトラブルも近年増えています。
アカウントを乗っ取られてしまうと、フィッシングサイトや架空請求などの不正な詐欺サイトの発信に利用されたり、自分のアカウントなのにログインできなくなってしまったりして大きな被害に遭うケースが後を絶ちません。
炎上トラブルが起こる
Twitterで共感されるツイートを投稿し、多くのユーザーがリツイートして話題になることを、「バズる」と言い、バズることを目的にツイートをしている人は一般人、芸能人ともに多くいますが、バズりたい気持ちが強すぎて過激な投稿をしてしまったり、間違って投稿してしまったりして、悪い形でバズってしまうことを「炎上」といいます。
一度炎上してしまうと、それを沈下させるのにかなりの時間と労力を要してしまいますし、名前や住所、勤務先や所属学校が特定されて個人情報をさらされるなど取り返しのつかない被害につながる可能性もあります。
詐欺被害
Twitterにはチケット詐欺と呼ばれる詐欺被害も横行しています。
人気のコンサートやスポーツ観戦のチケットが売り切れになっているタイミングで「チケット譲ります」という投稿が流れ、入金してもチケットは届かないという詐欺手口です。
被害者は「どうしてもコンサートに行きたい」という気持ちから、加害者に急かされるままに代金を入金してしまうことが多く、チケットが届かないという事実がはっきりするまで詐欺に気が付かないケースが多いのです。
自宅を特定されストーカー被害
Twitterでの投稿がきっかけでストーカー被害に遭うトラブルもあります。
Twitterでよく行くお店や家の近くの公園でのお花見写真を投稿したことで、写真に写っていた背景から生活範囲が特定されてしまい、付きまとい行為を受けてしまうような被害です。たとえ位置情報をオフにして投稿していたとしても、写真から生活圏内が特定されてしまうことも少なくないのです。
Twitterでトラブルに巻き込まれないための基本的な対策
Twitterには様々なトラブルの危険が潜んでいますが、基本的な対策をしっかりと守って利用すれば安全に楽しむことができるでしょう。
ここでは、SNSトラブルに巻き込まれないための基本的な対策についてご紹介していきます。
情報の公開範囲に気を付ける
SNSトラブル対策の大前提ですが、情報の公開範囲には十分注意しましょう。投稿内容やプロフィールなど、自分が入力した内容が公開される範囲を常に意識し、公開範囲をしっかりと考えて設定してください。
特に多くのSNSサービスで、初期設定では公開範囲が広く設定されているものもありますので、サービスを開始する前に詳細な設定方法を確認して公開範囲を設定してください。
「出身地くらいいいだろう」と思って全体公開にする人も多いですが、オンラインサービスの中にはログインに必要なパスワードを忘れてしまったとき、「あなたの出身地は?」のような質問に答えることで、パスワードをリセットしてくれる機能がありますので、個人的な情報はたとえ一見大丈夫そうに感じてもあまり公開しないほうが無難です。
写真に含まれる情報に気を付ける
写真には、その写真がどこで取られたのかという位置情報が埋め込まれている場合がありますし、位置情報が投稿されていなかったとしても写真の背景から位置を特定される場合もあります。
また、家族で遠くに出かけている写真を投稿したことで自宅に空き巣に入られてしまう被害も多く発生しています。
写真を投稿する際は、写真からわかる情報がどういうことか常に意識しておきましょう。
リンクは安易にクリックしない
「宝くじに当選しました」「無料で差し上げます」というメッセージとともにリンクが送られてきてリンクをクリックするとウイルスに感染して情報が駄々洩れになってしまうこともあります。
たとえ友人からのメッセージであっても、マルウェアに感染したために送られている可能性もありますので、Twitter上にあるリンクは安易にクリックしないのが安全でしょう。
読む人を不快にさせないかよく考えて投稿する
Twitterでは不特定多数のユーザーがあなたの投稿を見ることができます。不特定多数のユーザーがいるということは、あなたと価値観や感じ方、捉え方がまったく違う人も含まれているということです。
あなたにとってみれば普通の意見でも、それを読んで不快になる人がいると、炎上トラブルや誹謗中傷トラブルを引き起こしかねません。
投稿前に、内容が適切かどうかしっかりと考えてから投稿するように心がけましょう。
重要な情報のやり取りをしない
これは特に企業のTwitterアカウント向けの対策ですが、守秘義務や秘密保持契約に基づいている漏えいさせてはいけない重要事柄をTwitterなどのSNSに投稿することは絶対に辞めましょう。
もし企業のSNSアカウントから情報漏洩してしまったら、損害賠償請求につながる可能性もあります。
事実かどうか不明確なものは投稿しない
事実かどうかはっきりしない内容について投稿したり、それに対して意見を投稿したりすることも炎上トラブルを招きやすいので避けてください。
最近では、新型コロナウイルスのワクチンや飲み薬、戦争関係の事柄について、専門家も含め様々な意見がありますが、絶対に真実と言えるものがどれなのか不確かである場合は、SNSへの投稿は避けたほうが無難です。
他人のプライバシーや個人情報を発信しない
Twitterなど不特定多数のユーザーが見ている場では他人のプライバシーに関する情報を投稿しないようにしましょう。
「芸能人の●●を▲▲駅で見た」などという情報も他人のプライバシーに触れる情報になるので避けるべきです。
また、個人情報の発信に関しても注意が必要です。送る先がダイレクトメッセージであったとしても、送信先をミスしてしまう可能性もありますし、相手がなりすましアカウントである危険性も考えられるため、Twitter上で個人情報のやり取りは絶対にやめましょう。
センシティブな内容にはむやみに触れない
こちらは特に企業のTwitter公式アカウントでの対策ですが、企業アカウントの場合、Twitterを含めSNSをにぎわわせている話題には触れないほうが懸命です。
それらの話題に反応すると、世間の目も行きやすいですし、企業全体の意見として捉えられてしまうため、炎上トラブルの格好の餌食になってしまいます。
仮にそのような内容に触れる投稿をする場合は、SNS運用担当者の個人アカウントではないことをしっかり認識したうえで、投稿内容が会社のイメージダウンにつながる可能性がないか吟味して投稿するようにしましょう。
Twitterで誹謗中傷を受けてしまったら
誹謗中傷を含めたTwitter上のトラブルに巻き込まれないための基本的な対策をお伝えしましたが、万が一誹謗中傷を受けてしまったらどうすればいいのでしょうか。
誹謗中傷ツイートの削除依頼をする
Twitterは他者への嫌がらせや暴力などの行為を公式の「Twitterルール」で禁止しています。
「ヘルプセンター」にある問い合わせフォームから、違反ツイートを通報し、削除依頼をしましょう。ただし、通報したから必ずしも削除されるというわけではなく、Twitter社が問題のツイート内容や投稿者の違反歴をチェックした上で、最終的にツイートを削除するかどうかを決定します。
犯人を特定する
Twitterは多くの人がニックネームや匿名でアカウントを作成しており、誹謗中傷をする人の場合、ほとんどが匿名で誰が誹謗中傷をしているかわからないようにしているはずです。
そのため、誹謗中傷を受けたらまずは犯人が誰であるのか特定するという対応になるでしょう。犯人であるという明確な証拠とともに誰であるかを特定することで、誹謗中傷を辞めさせる法的措置などを取ることができます。
なお、犯人を特定するのは決して容易ではありませんので、SNSトラブルに強い探偵に相談して調査を依頼するのがお勧めです。
関連記事:発信者情報開示請求して誹謗中傷投稿者を特定しよう!流れとポイント
慰謝料請求を行う
誹謗中傷をした加害者の特定ができたら、責任追及を検討していきます。不法行為に基づく損害賠償請求や誹謗中傷により精神的苦痛を受けたとして慰謝料請求が考えられますが、いずれの場合も弁護士に交渉を依頼するのがスムーズでしょう。
なお、慰謝料請求や損害賠償請求などの法的手段を取る場合は、犯人を特定する証拠はもちろん、被害を受けているという証拠も必要になりますので、合わせて探偵に調査を依頼する必要があります。
Twitterアカウントの乗っ取り被害について
続いてはTwitterアカウントの乗っ取り被害についてです。アカウントの乗っ取りは多くの方がどこか他人事のように感じているのではないでしょうか。
「スマホを落としたこともないのにどうやって乗っ取られるのだろう」と乗っ取られる仕組みや手口がよくわからない方も多いと思います。
ここではTwitterアカウントの乗っ取りについて見ていきましょう。
Twitterアカウントが乗っ取られる仕組み
単純な手口としては、Twitterに登録しているIDやメールアドレス、パスワードといったアカウント情報を盗まれて、不正ログインされるケースです。
ログインIDはメールアドレス、電話番号、ユーザー名のいずれでも可能ですので、SNSのアカウント情報を見ればログインIDがわかってしまいます。そのため、パスワードさえ把握してしまえばアカウントが簡単に乗っ取られてしまうのです。
銀行のパスワードなどは慎重に設定する人が多いと思いますが、SNSのアカウントパスワードは誕生日や名前など単純な組み合わせにしている人も多いため、案外簡単にバレてしまうのです。
そして、意外と狙われやすいのが、企業の公式Twitterアカウントです。企業のSNSアカウントの場合、複数の人間でSNSを管理しているため、犯人は公式アカウントの企業関係者をよそおって「パスワードを忘れた」などと問い合わせ、パスワードを聞き出す手口を使います。
アプリ連携にも注意
乗っ取りの手口としてアプリ連携が使われることもあります。Twitterではほかのアプリと連携して利用できる機能があるのはご存知の方も多いでしょう。とても便利な機能ですがこのアプリ連携機能を悪用してアカウントを乗っ取る手口もあるのです。
たとえば、ツイッター上の記事やメールなどから詐欺のサービスサイトに誘導し、サービスを利用するためにTwitter連携をさせて、アカウントを乗っ取るのです。
なお、連携を誘導する詐欺サイトは、無料で見られるアダルトサイトであったりお金が当選したという偽のサイトであったりと利用者の心理を巧みについてくるものが多くなっています。
アカウントが乗っ取られているかどうか確認する方法
アカウントが乗っ取られてしまうと、自分になりすまして勝手にツイートをされたり、他の人にさらなる詐欺の元となるダイレクトメッセージを送られたりしてしまいます。つまり、あなたが知らないうちに加害者のような形になってしまうのです。
Twitterアカウントでの乗っ取り被害を減らすためには、日頃からTwitterをチェックしておくことが大切です。自分のTwitterが乗っ取られているかを確認する方法は以下の通りです。
・自分のタイムラインに身に覚えのない投稿がないか
・ログイン履歴は自覚があるか
・自分のアカウントから身に覚えのないDMが送信されていないか
・Twitter社からアカウント乗っ取りの通知がないか
・なにも変更していないのにアカウント情報変更の通知が来ていないか
これら一つでも当てはまっていれば乗っ取られている可能性があります。
万が一アカウントを乗っ取られていたら
万が一、アカウントが乗っ取られてしまった場合は、まず家族や知人、友人にTwitterアカウントが乗っ取られたことを連絡してください。自分でTwitterにログインができる場合は、すぐにパスワードを変更して非公開にしてください。
もしTwitterにログインできない場合は、Twitter管理会社に連絡をして指示に従って対応しましょう。
また、もしも乗っ取られたアカウントのIDやパスワードを他のサービスでも使いまわしている場合は、すぐにパスワードの変更を行うようにしてください。
もしもTwitterで炎上トラブルが起きてしまったら
もし自分のTwitterアカウントで炎上トラブルが起きてしまったら、どのように対応するのがいいのでしょうか。
ここでは主に企業の公式アカウントでの対応を見ていきましょう。
まずは冷静になる
炎上トラブルが公式アカウントで起こってしまうと多くの方がそのショックで取り乱してしまうでしょう。
しかし、焦ってその場しのぎの対応を取ってしまうとユーザーにも「その場しのぎの取り繕い」と判断されてしまい、その後きちんと対応を取っても効果が無くなってしまいます。
まずは冷静になって今後のことを考えていきましょう。決して焦って対応を取らないようにしてください。
すぐに削除しない
炎上トラブルが起こると「炎上トラブルの元になった投稿を急いで削除しないと!」と思ってすぐに削除しようとしてしまいますが、必ずしもすぐに削除がベストアンサーというわけではありません。
たしかに早期の対処は良いことですが、ほかの対応をしないままに問題の投稿の削除だけをしてしまうとユーザーからは「隠ぺい」と捉えられるリスクがあり、さらに炎上トラブルが加速する恐れがあります。
削除を行う前に、どのように対応していくかしっかりと話し合いましょう。
全体の方針が固まったらしっかりと謝罪を
炎上トラブルの対応においては一貫性があることが何より大切です。そのため、会社全体で対応の方針を決め、それが固まったらそれに基づいて謝罪や削除などの対応を進めていきましょう。
問題の内容や対応の指針を関係部署の人間すべてで把握しておくことが重要です。
まとめ|自力では解決できない場合は専門家の力を借りるのがベスト
不特定多数のユーザーがいるSNSの世界では、トラブルが起こると取り返しのつかないことになることも珍しくありません。
また、自身の何気ない行動がトラブルを起こすこともありえます。
ご自身でもできる対応策もありますが、自分一人ではどうにもできないようなトラブルになってしまうこともあります。その際は、一人で無理をせず、SNSトラブルの専門家に相談するようにしましょう。あなたの味方になってくれる人が絶対にいるはずです。